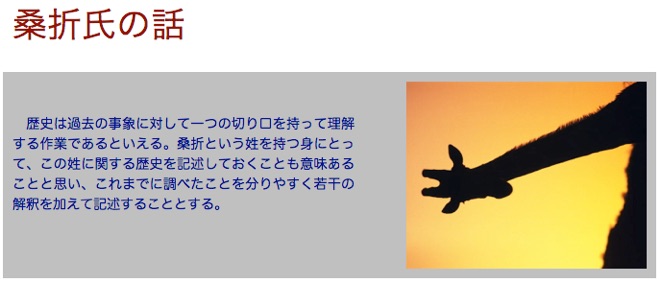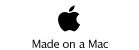桑折氏の話-7
<宇和島藩創設前後>
桑折宗茂の妻は石母田家の女で、13人の子をもうけたとされ、政宗死去の際に殉死したとされる7男もいる。中でも重要な2男2女をもうけている。長男は切腹、次男は還俗し、宗長、点了斉として跡を継ぎ、長女は石母田家、次女は飯坂家に嫁している。点了斉の跡の政長は朝鮮で亡くなった為、石母田家から養子を迎える。石母田景頼の息子重長が養子(政長の娘吉菊と結婚)となるが若くして亡くなったため、景頼が政宗の命により桑折家を継ぐ。景頼は石母田家に嫁した景長の長女の長男であり、政長や政長の妻の従兄弟にあたる。政宗の活躍に際して大きな手柄を立てたことでも知られている。
政宗が秀吉の小田原征伐に際し、政宗を呼びつけたときは政宗の大きな危機の時だった。弟を殺し、3人の信任する城代を置き小田原に向かった。この一人が石母田景頼である。温厚で、政宗の信任が極めて厚かったとされる。景頼は桑折政長の妹を妻としている。
飯坂家に嫁した次女は2人の娘を産み、長女は朝鮮で客死した桑折政長の妻、次女は政宗の側室となった。この側室が飯坂の局(吉岡の局)で、政宗の長男秀宗の母である。男子の無かった政長の後、重長が早く亡くなったため桑折家を継いだのは母方の従兄弟ということになる。
政長は釜山で風土病のため亡くなったがこの時には原田宗時も亡くなっている。この原田(景長の孫に当る)を継ぐのも桑折景長の子孫(宗長の子、宗資)である。
伊達秀宗は側室の子であった為、仙台で無く、宇和島藩の藩主となった。この時、母親飯坂の局も同道する。桑折家では飯坂の局の姉(桑折政長の妻)と養子景頼が宇和島に向かった。このあたりではその前に亡くなっていたという説もある。景頼は左衛門を名乗り桑折左衛門と称した。桑折景頼は筆頭家老、7000石で秀宗を補佐した。跡を継いだ宗頼の代に6000石を減じ、1000石となった。その後、秀宗の4男宗臣を養子として迎える。宗臣は「むねしげ」と呼ぶ。中興の祖10世宗茂を意識したとも考えられる。同時に秀宗からすれば恩義ある豊臣の一字を持っているとも言える。
このような経緯を見てくると、宇和島伊達藩の創設とそこに付く家臣団からは天文の乱で守護代となった桑折貞長の血を引く一族が宇和島に移ったという構図にも見える。
政宗の差配は極めて周到と思われる。桑折家を石母田景頼に継がせ、宇和島伊達藩創設に向かわせたあたりは一族の血筋を意識していたとしか思えず、考えさせられる。
桑折景頼は桑折家の墓を宇和島に持っていった。太祖心円入道と景長以降の位牌は宇和島の等覚寺にある。
<吉菊のその後>
桑折政長の跡を継いだ重長は若くして亡くなり、息子も2歳だった為、重長の父景頼が跡を継ぐ事となった。重長の妻、吉菊(政長の娘)は若かった為、天童家に再嫁することとなった。娘を儲け、長女に伊達の涌谷の分家から次男を婿養子にむかえ、天童家を継がせた。後に涌谷伊達家を継いだ長男が亡くなったため、天童家を継いだこの次男が戻り、涌谷を継ぐこととなった。伊達騒動で原田甲斐に殺されたとされる伊達安芸である。原田甲斐は桑折景長の曾孫、伊達安芸の義母も景長の曾孫である。伊達騒動の登場人物はこうした一族のしがらみの中にある。
<播磨屋形>
桑折町にある播磨屋形の跡地は広大なものとされる。宇和島藩に移る前の桑折家の屋敷跡とされる。実態も格式もおそらく大名家に引けを取らないものだったのだろう。
この名称は景長が播磨守、伊勢守などの官位を名乗っていたことに由来しているとされている。
伊達晴宗が奥州探題になったとき、桑折景長は守護代となっている。この時代、官位は奥州の地ではそれなりのものだったと思われるので、播磨守、伊勢守の呼称はそれなりに中央との関係で得た官位と思われる。播磨守は平清盛の官位でもあり、どのような経緯で名乗ったのか気にはなるが調べきれていない。
このような格式から7000石の宇和島伊達藩初期の状況があったと思われる。
伊達の創業の地は江戸時代には幕府直轄の桑折藩となる。関所機能が設けられ奥州へのかなめの地として認識されていたのかもしれない。近隣に江戸時代に開発された半田銀山もあり豊かな地でもある。