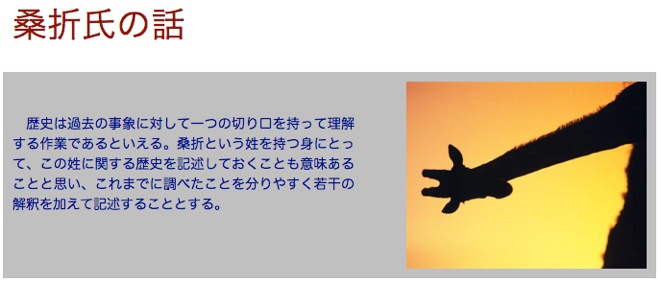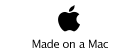桑折氏の話-11
21世徳翼は桑折桂円の名で知られる文人だった。若い頃の書は才気煥発を感じさせる書だが蔵が焼けたため記録は残っていない。宇和島に残る資料でもあればまとめておきたいところではある。桂円の事績はいくつか残っていると思われるので分かった時点で追加することとする。桂園の時代は伊達村壽の時代に重なりその間、宇和島藩は経済的には困窮していたとされる。ただし多くの次世代に向かう施策は練っていたようで中務と呼ばれる桂園や図書と呼ばれる松根図書の意見を求めるさまなどが残されている。
22世長よしの「よし」の字は人名用漢字にもない字の為ひらがなで書くしかない。宇和島郊外の松野町の資料によれば長の字が違っているが家系に伝わる字は長なのでこれで残すことにする。
21世徳翼は長女の次男長よしを養子として22世とした。長女は小池家に嫁しており小池一大夫宣哲の次男となる。徳翼の代で桑折氏の詳細な系図を作ったとされ、それを完全に受け取ったうえで一つの区切りをつけた代の様に思われる。村壽、宗紀、宗城、宗徳に関わった記録がある。時代は宇和島伊達藩の経済状況が良くなってきた時代でもあり、宇和島伊達藩としての活動ができてきたように見える。宇和島藩が村壽から宗紀に藩主を交代した時期、長よしがまだ若かったころ藩の財政が借入金のため逼迫し大坂の債権者と交渉に行くさまが残っている。桑折中務、武田仁右衛門、松田源五左衛門の3人で赴き30万両の借入金を無利子200年賦で妥結したとされる。このころ薩摩藩でも500万両の借入金を250年賦にしたことが知られているがほぼ同程度の功績と思われる。武田仁右衛門はこの功績で恩賞を得ている。
江戸へ出る機会もあったようで仙台の綱長の子孫と会ったことが記録されている。このころには仙台では桑折氏の記録は残っていなかったようで新鮮に受け取られているさまが見て取れる。
長よしは桑折左衛門が宇和島桑折家の祖と認識し照源寺に有った左衛門の墓を等覚寺に移し、照源寺には左衛門の事績を記した碑を作った。
等覚寺の桑折宗臣の墓には古い墓がいくつも残っている。長よし以降の墓はそれなりに読めるがそれ以前ははっきりしない。左衛門は四国に太祖心円入道と宗茂以降の位牌を持ってきたとされ、太祖心円入道と9世までは合祀したとされている。この墓は松野町の照源寺にあったのかもしれないが、長よしの時に改めて整備したのではないかと思う。
奥にある長よしと同時代と思われる墓がこれらのものと思われるが調べてみたいところではある。
長よしの代になると宇和島藩も経済的に立ち直っており、対外的な活動も活発になってきている。長よしの妻は松根図書の娘で、長男の紀望(のりみ)が23世となる。
松根図書は幕末の宇和島藩家老として有名だがこの松根図書は年代的に合わずその先代もしくは先先代になると思われる。妻の生年は1810年、幕末の図書の生年は1827年になり17年若い。この時代は世襲と階級が固定されていた時代で桑折氏は長よしも紀望も中務を名乗っている。中務は名前の通り城代家老の任務にふさわしい。今でいえば総務担当といったところか。松根図書に関してはネットの情報は少なく先代や先先代が同じように図書を名乗っていたか否かは定かでないが調査部、企画部といった役割を思わせるこの名前は調所、中務といった呼称と同じような役割に基づく呼称なのではないかと思われる。
21世徳翼には氏秘という実子の長男がいるが神尾家に養子で出ている。いわくありげな名前だが理由はわからない。氏秘の妻は伊達村壽の娘でこの夫婦の娘、神尾幾が23世、紀望の妻となる。この辺りの理由などは分かっていない。長よし、紀望ともに駿河や播磨の名を名のっている。幕末には時代の変わり目として名を変える空気があったのだろうか?いずれもかつての桑折氏が名乗っていた名前の範囲ではある。
長よし、紀望の代では江戸や京都へは何度も出かけているようだ。長よしは徳翼が望んで後継者にしたところからも優秀だったのではないかと思われる。駿河を名乗っていた理由が気になるがわかっていない。駿河伊達家は常陸入道念西の4人の息子のうち4男が独立したとされ、江戸時代には紀州藩の家老職を務めていたとされる。あるいは交際もあったのだろうか。
紀望の代は幕末の宗城の活躍と重なっており長州征伐、松山征伐、函館征伐への参加などが記録として残されている。村田蔵六が宇和島にいた時に主として対応していたのが当時、桑折駿河を名乗っていた紀望だったようだ。筆まめな村田蔵六は何度か桑折駿河宛に手紙を送ってきている。紀望がこれらの活動を明治3年で辞め名前も紀望に戻し政治的活動を終えた理由もはっきりしない。慶応3年12月8日の小御所会議の前、伊達宗城は京に出ていた。おそらく当初のシナリオでは大政奉還後、公武合体派が担ぐ徳川慶喜を立てた政権を築きその枢要なメンバーとして新時代に向かうはずだったと思われる。小御所会議の結果クーデターは成功し当初の思惑とは異なる役割を持つこととなったのではなかろうか。奥羽越列藩同盟の盟主が仙台伊達藩になる中でそれなりにややこしい話があったのではないかと想像される。伊達宗城は宗紀の養子として藩主となったが宗紀の子宗徳を養子として後継者とした。一方で長男は松代真田藩に養子として出て藩主となっている。仙台伊達藩一代藩主としても息子を送っている。
紀望の紀は宗紀に由来すると思われる。紀望の次が城方で宗城に由来すると思われる。
紀望の子、城方は東京で育ったと思われる。慶応義塾を出ており2016年が100回忌とされるので福沢諭吉に師事した可能性がある。城方の妻は宗城の7女順である。
時代は明治になりこの後の歴史は近現代史になり資料は豊富になる。桑折氏の過去の記述はここまでとする。