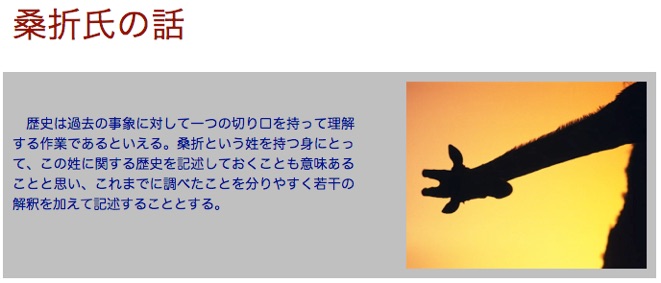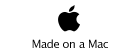桑折氏の話-1
歴史は過去の事象に対して一つの切り口を持って理解する作業であるといえる。桑折という姓を持つ身にとって、この姓に関する歴史を記述しておくことも意味あることと思い、これまでに調べたことを分りやすく若干の解釈を加えて記述することとする。
仙台伊達藩では伊達政宗を初代とする家系図を持っているが、伊達家ははるか前からの歴史を持っている。政宗の祖父の時代に起きた天文の乱の記憶もあり、政宗に始まる新たな伊達の歴史を築こうとしたともいえるように思われる。桑折氏の歴史はこの前の時代抜きにはありえないように思われるので、歴史に見ることの出来るところから記述を始めようと思う。
<前史>
桑折氏は伊達氏の庶流である。伊達家3代義広の庶長子親長が初代桑折氏を名乗ったとされている。従って、まずは伊達氏のことから記述を始めることとする。
伊達氏は後述するように鎌倉時代に誕生する。それ以前は伊佐氏と称し、常陸の国の武士、現在の下館近辺にあった伊佐荘、中村郷を領していた。
伊達家の正史では「先祖は藤原不比等の流れを汲む魚菜公に遡る」とされ、伊佐氏は常陸の国中村郷を領した藤原を祖とする流れとされている。藤原氏山陰(やまかげ)中納言は讒言にあって常陸の国に流されたとされ、その末が伊佐氏であるとされている。北家房前5男魚菜5代の孫が山陰で、山陰6代の実宗が伊佐氏を名乗ったとされる。実宗は実力者だったようで、鹿島神宮を建立したとされている。そのためかのちの伊佐氏は鹿島神宮の造営奉行などを務めている。また、当時飢饉で大変だった頃、大蔵卿の大江氏に頼んで税の免除を願ったりしている。
藤原氏山陰中納言は藤原不比等の曾孫に当たる魚菜公の5代後になる。系図算用によると常陸介の呼称が見られ、それなりの地方任官の歴史があったと思われる。
伊佐の荘は今の下館のあたり、当時の交通の要衝でもあった。近隣には川を挟んで、有名な結城一族がいる。こちらも藤原一族で秀郷流とされ、奥州藤原と祖を一にする名流である。平将門を破った藤原秀郷を祖とする。魚菜公の時代で分かれるがやはり魚菜公の5代後に当る。平将門の乱の折には藤原秀郷が討伐に成功したが、同時代に山陰中納言もこのあたりにいたと思われる。平氏、源氏、藤原と貴種伝説と相まって、このあたりの先祖特定は困難といえる。
後に出てくるが頼朝の奥州征伐で先行し勝利を収めたのが伊佐氏、本陣で戦ったのが結城氏とされる。常陸の国には後々まで伊達氏と争う佐竹一族がいる。こちらは平氏の一門とされ、初期には頼朝と戦い、奥州征伐で頼朝方に着き、この地方の雄として戦国時代を争った。
因みに、魚菜公と同じ藤原北家の流れには魚菜公の前に分かれた藤原純友がいる。純友の乱を起こした藤原純友は宇和島の沖にある日振島を拠点として活動したとされ、後世の宇和島伊達藩を考えると因縁といえる。
<藤原と常陸>
藤原不比等は持統天皇の時期、参謀として日本書紀を書かせたといわれ、奈良時代を確立した人物として知られている。多数の子孫を残し、戦国時代の多くの大名が藤原の子孫と称している。奈良時代を通じて、地方平定に当たって、多くの武力集団を率いる機能を持っていたと考えてよいのではないかと思われる。藤原不比等は大化の改新の藤原鎌足の息子であり、鎌足もまた関東、東北の地にゆかりがある。
大化の改新で名をあらわした鎌足は常陸の国の出身という説がある。鎌足の出自は事実と異なるようだが、藤原氏の先祖が常陸の国とされるのは事実のようである。藤原氏は中臣氏を称し、鹿島神宮を奉じている。蝦夷平定でこの地に来たのは藤原だけでなく、平氏、源氏も同様で、いずれもその後の有力武将となっている。
中央との往来も江戸時代などより機動的に行われ、幹線道路はかなりの広さを持っていたとされる。主要な交通路である東山道、東海道などの奈良時代の道幅は江戸時代よりずっと広く、12mに達しているとされ、機動的な兵の配置が可能だったと思われる。
<常総に伝わる説>
中世常総名家譜には常陸時代の伊佐氏のことがかなり詳しく載っている。伊佐氏の祖は藤原山陰に発し、藤原鎌足の8世の孫、その子に越前守安親があり、為盛、定任、実宗と続く。この実宗が1099年陸奥守となり鎮守府将軍を兼ねた。1111年常陸守となる。この年、臨時課役が課され疲弊していたことから大蔵卿の大江匡房に哀訴し助かったとある。1114年実宗は鹿島神宮を造営したともある。伊佐氏の祖はこの実宗とされている。
大江氏は後に鎌倉幕府に参謀として参画する。常陸に残る系図では伊達初代朝宗は鎌倉幕府の鎌倉中として参画した常陸入道念西の父とされている。鎌倉幕府の中で新時代を築いたことから新たな系図を作ったとも考えられ興味深い。これによれば朝宗の長子は早世し、二男が念西、のちの伊達宗村となる。
伊達の正史では念西が伊達初代とされるが、いくつかの資料を見てくると、家系図は大きな歴史変動を契機として書かれ始めている。実際に住み始めたのは念西と思うが、伊達初代は鎌倉中(鎌倉幕府の中核をなした優良御家人150人ほどの称)に参画した先代の念西の父を当てたというのが真実のように思われる。
この説では2代が念西、3代が念西の長子為宗が改名し義家として継いだとされている。のちに記すが、念西の4人の男子のうち圧倒的な存在感を持っているのは為宗であり、念西の後の3代を為宗が継いだというのも妥当と思われる。一般には二男為重が伊達2代とされるが、吾妻鏡に見られる次郎伊達は但馬伊達を指しており、貞曉を担いだ策謀などのことが載っていることからも次郎為重は伊達本家を継いだのではないと思われる。
この説によれば桑折家初代は為宗の子ということになる。