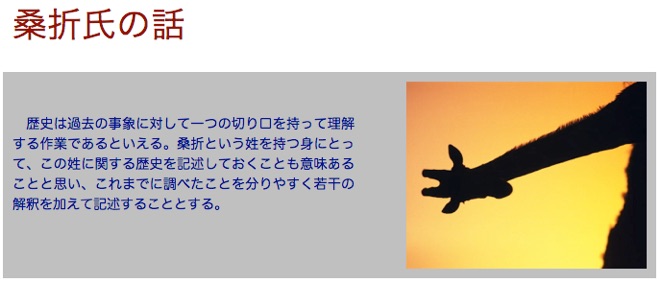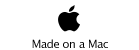桑折氏の話-2
<伊達の始まり>
伊達氏の名が歴史に登場するのは吾妻鏡からとなる。鎌倉幕府の正史である吾妻鏡で伊佐の姓で登場するのが伊達氏の祖で、後世の注では伊佐(伊達)氏と記載されているものもある。伊佐氏は常陸の国の武士とされ、今の下館の辺り、伊佐荘中村郷を所領とする奈良時代から続く家柄とされる。常陸入道念西が最初に登場する伊佐氏の惣領である。娘を源頼朝夫人として送り、長男の為宗を頼朝配下とした。為宗は有能であったと思われ、吾妻鏡にはしばしば登場する。初期には皇后宮権小進という肩書きの時が多い。後に大進に昇進し、その関係で頼朝夫人であった妹は大進局と称されている。大進局は男子貞暁(じょうぎょう)を設けたが、貞曉は北条政子への配慮から京都の仁和寺に預けられている。これらの記述を見ると、伊佐氏はかなり頼朝に近い立場だったといえそうである。吾妻鏡は鎌倉幕府の正史である為、要所のイベントを除くと儀式的な記述が続く。イベントの一つ、頼朝の奥州征伐は平家討伐後、奥州藤原を征伐し、鎌倉幕府を磐石にした戦いである。伊佐氏はこの戦いで戦功を挙げ、伊達の地を手に入れることと成った。
常陸入道念西には4人の息子がおり、長男為宗、次男為重、三男資綱、4男為家が奥州征伐の戦いに出陣した。藤原泰衡軍の前衛は今の福島県伊達郡に置かれており、ここが最初の戦闘の地となった。伊達の大木戸として奥の細道にもでてくる地名はこの時、泰衡軍の築いた砦の大木戸に由来している。阿武隈川の水を堀の内に引き込み、要塞を築いていたと記述されている。泰衡軍の主力は厚樫山に置かれ、緒戦は「厚樫山の戦い」とされる。現在の福島県中通に当たる信夫地方は奥州藤原の重臣佐藤一族が代々治めていた地である。この戦いで4人の兄弟は秣の中に甲冑を隠して運び、奇襲攻撃を懸け、泰衡軍の重臣佐藤兄弟を始めとする敵軍の首級18を挙げたとされる。中でも為宗は獅子奮迅の働きとある。はっきりした論功行賞は吾妻鏡には出てこないが、伊達家に残る記述では、この功によって伊佐氏は伊達郷を手に入れることになったとされている。
ここに現在、福島県の中通と呼ばれる地域を領土とする伊達氏が誕生する。以来領土を拡大、領土を接する大崎(宮城東北部)、浜通(福島海岸部)、会津、出羽(山形)と同盟を結び、板谷峠を超え、現在の山形県置賜地方を押さえ、米沢を所領とすることとなった。
米沢にまで進出し越後の上杉、会津の蘆名氏と接する戦国時代を迎える。伊達郷は明治時代、福島市に日銀支店が置かれたことでも分るように東北、奥羽、会津への交通の要衝であり、350年間ここを押さえていたことは軍事、経済の両面で極めて大きなことだったといえる。
奥州藤原氏の前線基地である伊達郷は関所機能を持ち、移住後、早い時期に伊佐荘の2倍に達する規模になっていたと想定されている。
<鎌倉街道>
因みにこの時、頼朝や伊佐兄弟が進軍した道は鎌倉街道中道と呼ばれる街道で、奥州道とも呼ばれた。鎌倉-溝口-渋谷-池袋-川口-春日部-杉戸-古河-小山-宇都宮-白河の関から奥州へと続く古代の幹線道路である。部分的に残る都内の鎌倉街道が何本か現存する。世田谷、杉並を通り、善福寺川沿いの大宮八幡神社を経て、大宮、上尾へと抜ける道は有名である。私の父が購入した浜田山の地のすぐ脇に現在もこの鎌倉街道が残っている。
伊達正史によると常陸入道念西は次男為重を連れて伊達郷に入り、伊達朝宗と称した。現在、福島県伊達郡桑折町満勝寺に残っている墓は4代政依によって作られたといわれている。代々の伊達氏は周回の際など必ずここを参拝したとされている。
伊達正史と異なり、駿河伊達家に伝わる資料によると、初代の朝宗は常陸入道念西の親となっている。この説に従えば念西は次男為重、後の伊達宗村ということになる。この説にも幾つかの裏づけはあるとされ、念西が2代目とする資料もある。古い時代のこととしてこれも定かでない。
後述する常総に伝わる説が最も説得力に富むように思われる。念西は二男だが長男が早世したため後を継いだ。念西は吾妻鏡に再三出てくるところから為重ではあり得ない。念西の父が鎌倉中に参加し新たな時代を作った。その後念西の4人の息子の藤原征伐での活躍で伊達の地を手に入れることとなった。念西は伊達の地を治めた。安定した時点では伊達が伊佐の地の2倍に達する規模となった。念西は父を初代とする伊達の系図を作った。吾妻鏡では次郎伊達は但馬を指しており、為重は但馬の地にいたと思われる。伊達の地を手に入れるにあたっての最大功績者は為宗でその活躍は群を抜いている。念西の後を為宗が継いだと考えるのが妥当と思われる。この説では初代朝宗は念西の父、2代宗村が初代の二男念西、3代義広が為宗ということになる。
<伊佐氏のその後>
常陸入道念西の長男為宗は常陸の地に残った。伊佐為宗の名前は吾妻鏡にその後も登場する。例えば、当時、常陸国の総社であった鹿島神宮は今の伊勢神宮と同様、20年毎に遷宮を行う決まりがあり、その建造奉行になっていた為宗が工事の遅れに怒ったなどという記述が残っている。この頃には念西入道伊達、伊佐為宗、伊達次郎為重はそれぞれ伊達入道、伊佐、但馬伊達(次郎)として吾妻鏡に登場し、伊達一族として遇されている。
伊達が勢力を持つにつれて、伊佐、伊達(入道)、伊達(次郎)は鎌倉幕府では一族として遇されていたようである。一族は鎌倉中と呼ばれる鎌倉幕府の優良御家人130名あまりの格で序せられている。鎌倉中は鎌倉幕府の有力御家人を指し、鎌倉在住が原則であった為、伊達惣領は鎌倉に住まいしていたとされる。念西の次男為重は大進局の息子である甥の貞暁を還俗させ、鎌倉幕府の将軍とする工作に失敗し、但馬(兵庫県)の地に封ぜられたとする説もある。諸説あるが、当時、但馬の地に伊達領があり、但馬伊達(次郎)が一族とされていたことは事実のようである。伊佐氏のその後は定かでない。常総に伝わる為宗が伊達3代義広となり、伊達と伊佐が統合されたと見るのが自然と思われる。江戸時代、下総、龍ヶ崎の地は伊達家の所領であったがこの関係か否か定かでない。
鎌倉時代初期、大進局が男子を設けたこともあり、頼朝の愛妾であった事なども寄与してか、複数の土地を手に入れている。但馬の地は伊達家の豊富な富の寄贈によるものか、鎌倉幕府の都の監視目的か定かでない。富の比率は入道伊達の伊達地方が70%、伊佐が20%、但馬伊達が10%であった。
<次男が継ぐ伊達>
伊達氏は次男を跡継ぎとすることで知られていた。もともと、次男が故郷を離れて新規に獲得した地を開拓して行った歴史が背景にあるのかもしれない。後には長男が世継ぎとなったが、後の政宗も藤次郎(弟は小次郎)を名乗っている。政宗の父(輝宗)、祖父(晴宗)、曽祖父(たね宗)も長子であるが次郎を名乗っていた。3代義広が為宗とするとこの点が引っ掛かる。4代政依が次男であること、3代までの経緯がはっきりしないことを考えると、次男跡継ぎ説は4代頃にできたとも思われる。桑折氏初代親長と政依とはともに時宗に帰依し、政依は初代朝宗の墓を伊達の地に作ったとされている。伊達の系図はこのころに作られ始めたとみてよいように思われる。
<その他>
駿河伊達家は念西の4人の息子のうち4男為家を初代とする系図を持っている。戦国時代は今川、真田などと親交を結びながら活動したとされている。後の江戸時代、紀州徳川家の家老職を担っていた。幕末にはしばしば登場する。この子孫に明治時代の陸奥宗光がいる。陸奥の苗字は先祖の伊達家に由来してつけたとされている。
系図算要によると伊佐兄弟の上に伊達3代が来る形になっているが吾妻鏡の記述が無理の無い形と思われる。
<貞曉(じょうぎょう)のその後>
大進局の子、貞曉は文治2年(1186年)に生まれる際、大江広元の息子、景遠の屋敷を産所としている。北条政子に疎まれたことから、頼朝は貞曉を早い時期に京へ送り、安全を確保していたといわれている。元々貴族の出であった大江家の景遠、景国親子の庇護の下、貞曉は仁和寺の僧、隆曉の弟子となり、隆曉の死後、仁和寺勝宝院を継承する。後、承元2年、高野山の僧となり、高野聖行勝に就き、行勝の死後一心院別所を継承する。後年には頼朝の血を引く高僧として基盤の安定を果たした後の北条家からも敬われるようになり、北条政子は貞応2年(1223年)高野山に金剛三昧院を建立している。(鎌倉源氏三代記:永井晋)このような関係の中で、但馬伊達の存在がある。この時期から伊達家が京と近い関係を持っていたことが分る。
大江家と伊佐家の関わりは系図算要によると藤原魚菜から数代後、念西の甥の母(義姉)は大江家から迎えているとする記述があり、血縁でつながっていた可能性がある。このあたりの藤原は皇后宮小進、大進の官位を持っているものが多く、為宗の官位と見比べ、関わりはあるものと思われる。
貞曉は源実朝の弟であり、このような生涯をおくった。鎌倉2代頼家の息子、禅曉は似た境遇で仁和寺にかくまわれたが、北条家によって殺されている。
因みに大江広元は毛利家の祖としても知られている。島津家とも関係があるとされ、戦国時代の大名家の妙な因縁を感じる。宇和島伊達家と毛利家も強い交流関係を持っていたとされ、幕末の動きにまで関連しているのは興味深い。
<常陸に残る伊達の記録>
常陸の国には伊佐為宗が残った。常陸の地に残る為宗のその後はあっておかしくない歴史と思われる。それによると、伊達に移住後の4兄弟の関係は密なもので、伊達4代政依は為宗の子とある。為宗は6尺豊かな偉丈夫で伊佐の地で活躍したのち、伊達郷に入り3代義広を名乗ったとされている。次郎が但馬伊達とされ、貞曉を担ごうとして失敗した等との記述を見ると、為宗が伊達3代になり、二男為重が但馬に移った図は考えられる。いずれにしろ、伊達が誕生したのちに、伊佐、伊達、次郎伊達と3つの地名が一族を指しているところを見ると相互交流は密度の高いものだったと考えるべきだろう。政依の兄が桑折家初代となっているが、父親が異なっていた可能性も否定できない。この当時は鎌倉中の一族で、伊達、伊佐の棟梁は鎌倉に住む場を持っていたと思われる。政依が鎌倉にいて、初代桑折の親長が伊達にいた図は十分考えられる。最も、政依が為宗の子とすると為宗の死んだのは90歳を超えることになるというから遠い時代のこととして今では事実はわからないというべきなのだろう。
中世常総名家譜によると伊達初代朝宗は常陸入道念西の父となっており、鎌倉幕府に参画した時点を初代とする形になっている。従って念西は2代宗村ということになる。従って3代義広が為宗という流れとなっている。