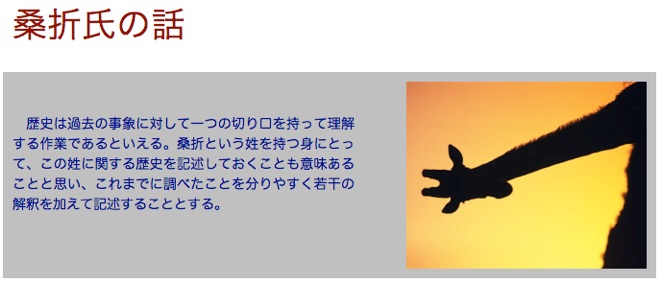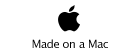桑折氏の話-10
<和霊騒動と桑折氏の減俸>
宇和島に和霊神社という神社があり、そこには山家清兵衛が祭られている。宇和島伊達藩創設後、総奉行を務めていた山家清兵衛は侍奉行の桜田玄蕃一味の讒言によって一族皆殺しにされた。その後、桜田玄蕃一味の事故死などがあり、たたりを鎮める為和霊神社に祭られたとされている。宇和島では和霊騒動として知られている。
山家清兵衛が総奉行として宇和島伊達藩創設時に活躍し、その統治も民の信頼を得ていたということは現在では定説となっている。和霊騒動と呼ばれる山家清兵衛一家の惨殺事件は長い間、悪役の桜田玄蕃一味が行ったものでそれを知った秀宗が後に清兵衛の無実を知り和霊神社に祭って慰霊したとされていた。この見解には異論もあり、現在では多くの資料の研究の結果、秀宗の命による上意打ちだったとする考えが主流となっている。
この事件の顛末に関してはいくつもの本が出ていてそれぞれに一定の根拠がある。ここではそれぞれの説の確認や検証を行うことは行わず、考えられる仮説を記述する。
宇和島伊達藩創設時に政宗は周到な人員配置を行っている。秀宗は秀吉の人質として京で秀頼とともに育ち、実戦の経験や統治の経験はほとんどなかったと思われる。戦闘や統治の現場で得られる腹心の家臣団も持っていなかっただろう。宇和島伊達藩の藩主として無事に立ち上げさせることはようやく太平の時代になりかかっていたこの時期ではまだ危険性を持っていたと思われる。
政宗の立場に立ってみよう。政宗における片倉小十郎のような腹心の部下を持たぬ秀宗のためにどのような布陣を取るべきと考えたろうか。伊達一門は一族の結束を高めるために複雑な親族関係を持っていた。秀宗の後ろ盾となって打って一丸の体制を支える体制の中核にこの親族関係を持った体制を考えたのではないかと思う。
秀宗の母親は飯坂局、桑折景長の次女が生んだ次女にあたる。姉は桑折政長の妻である。景長の長女は石母田家に嫁ぎその長男が石母田左衛門、後の桑折左衛門となる。
桑折景長の後を継いだ宗長の長男政長は秀宗の母の姉を妻として一女をもうけていたが朝鮮出兵の折、病で亡くなっている。後を継がせるため政長の娘由菊の夫として石母田景頼の長男重長を桑折重長として養子とした。この重長が若くして亡くなり子が2歳だったため政宗は石母田左衛門に桑折左衛門として桑折家を継ぐことを命じる。宇和島伊達藩創設のまさにその時期にあたる。桑折、石母田、飯坂、原田といった一族がどの程度の結束を持っていたか定かではないが後の伊達騒動に連座して一族がとり潰しになっていることからもかなりのものだったと考えてよいのだろう。
政宗と同年代の桑折左衛門を後見役とし縁戚関係にあり有能だった山家清兵衛を総奉行とする配置は政宗の直接任命とされる。若き日の政宗を支えた家臣団による宇和島伊達藩創設にあたっての配慮とも思われるが秀宗が任命する形にしなかったことの問題もあったのではなかろうか。百戦錬磨の政宗からすればこの配置は万全で、秀宗はこの神輿に乗っていればよいと判断していたのではなかろうか。後に山家清兵衛上意討ちに際して秀宗は自分の部下を成敗したつもりだったのだろうが、任命者の政宗の了解なく成敗する判断に怒りその事情説明を桑折左衛門に求めた背景にはこうした関係があるように思われる。
政宗がどの程度こうした結束を意識していたかについては判断があると思うが、天文の乱に関して残している記述や伊達成実の出奔と戻ってからの配慮などからみても熟知していたと思われる。
一方、桑折左衛門として名門桑折家を継ぐこととなった左衛門の立場ではどう考えたろうか。息子の重長が継いでいた桑折家をその夭逝のため親が継ぐことに成った。飯坂局の姉政長の妻はまだ存命だったと思うが左衛門のいとこに当たり同年代だが母親として遇したろう。政宗の命で桑折家の始祖心円入道、景長以下の位牌を持って宇和島に向かったとされる。桑折、石母田、飯坂といった秀宗の後ろ盾となる一族の有力者を纏めて新天地で立ち上がらせるためには左衛門ほどの経験と人脈が無ければ勤まらなかったと思われる。
3000人を超えたと思われる陣容の内1000人以上はこうした関係で固めていたのではなかろうか。
やがて、山家清兵衛の事件が起きる。政宗の部下と思っている政宗に対し「秀宗の部下を問題があると判断して成敗した」と思っている秀宗では食い違って当然だろう。桑折左衛門が江戸に呼ばれる。左衛門は経歴からしてもまた温厚とされたその性格からも秀宗を立てて藩を維持する必要があると判断したはずだ。どのような会話がなされたかわからないが、左衛門は若い秀宗を擁護し今後の体制に対しても前向きに述べる必要があったと思う。その中で政宗と自分の時代から次世代に代わることも語ったと思う。太平の世が訪れ河後森城の取り壊しもなされ10万石の中に7000石の領地があることの是非も論じられたかもしれない。政宗の隠居料に相当する3万石相当を生み出す地は後の吉田藩の地に相当する。
山家清兵衛が亡くなり政宗の構想した世界からずれてはきたがともかくも取り潰しは免れた。太平の世が近づき長く続く体制の構築が急がれる。左衛門は宇和島藩では河後森城のある河原淵領に住んでいたとされるが次世代では宇和島伊達藩との一体化をも考えていたのではなかろうか。左衛門は引退し、二男の宗頼が15世を継ぐ。ここで7000石から1000石への減俸となる。次代は左衛門の二男宗頼が継ぐがこの時には秀宗4男の宗臣の養子縁組の話がまとまっていたと思う。もともと左衛門の長男が継ぐはずだった桑折家だが不測の事態で左衛門が継いだ。山家清兵衛の事件を見ても次世代以降でどのようなことが起きるか予断を許さない。政宗とのパイプを持つ左衛門亡き後、山家事件の再来が起きないとも限らない。政宗、秀宗、左衛門協議の上で宗臣の桑折家への養子縁組の件がなされたというのが妥当な判断ではないかと思う。次世代の体制を考える際、秀宗の長男は病弱、二男が本命だったがやはり病弱だった。最終的に3男の宗利が2代目となり5男の宗澄が吉田藩に分藩することとなる。秀宗の晩年は病でよい評判は無い。この時期に藩の重臣たちの間では秀宗後の体制に関して集団指導制に持っていく努力をしていたと思う。結果として吉田藩の3万石での分藩が実現してしまったが、河原淵領の宇和島への統合が先になされ桑折宗臣は宗利と共同で統治にあたる形となった。
7000石から1000石への減俸は現代から見れば異様で様々な意見がある。中には桑折氏キリシタン説まであるがより大局観に沿った見方の方が妥当と思う。弱小な貧乏藩だった宇和島伊達藩発展の基礎を作るための体制づくり、吉田藩分藩問題を抱える中で一つにまとめるために行われた一体化という見方の方が妥当と思われる。
以前にも書いたが、宗臣の呼び名は「むねしげ」桑折景長の最後につけた名と同じ、臣の字は豊臣を連想させる。宇和島で育ち風流の世界を主とした生活を送った宗臣は桑折を継いでも宇和島に住んだのではないかと思う。桑折氏の墓所を竜華山等覚寺にしたのも宗臣が最初なのだろう。
この時、7000石を構成していた多くの人たちが生活の転換を余儀なくされたのだろうと思う。宗頼の流れが安貫や大和田や小池として後に桑折家存続に際して出てくるがこれらの流れはそうした側近たちだったのではないかと思う。中に武田家があり佐多岬の守りについていた一族がいる。後に伊達宗城の側室として多くの子を作り明治の活躍を支えた武田栄は京都の出身で武田家の養子として宗城の側室となっている。この武田が関連がある否か定かでないが重なっている可能性はあり得るのだろう。第2次大戦で宇和島も空襲を受け桑折家の蔵は消失した。この時期祖父の直はこうしたところに残る資料を集めて略記を作ったようだ。この過程で桑折氏の過去の事績に触れ改めて幾つかの資料を集めていたように見える。
宗臣は文人として知られ、文宝日記や大海集などを残し、事績も豊富なのでここでは付け加えることは無い。
この時期、政宗が亡くなり、伊達騒動が生じ仙台藩との関係が深まる。仙台藩側から支藩に持っていく動きのようにも見える。吉田藩の分藩、宗利の養子として仙台伊達藩綱宗3男を宗よしとして迎える。この流れの中で宗臣の子宗敷は宗よしの5男を養子として迎えたが夭逝、さらに弟を迎え宗恒が18代となった。しかし8歳で亡くなり。伊達家からの養子の流れは終わる。
18代で迎えた宗恒が早世したため左衛門の二男宗頼の子頼安が起こした分家から安貫家に養子で出ていた安貫が19代となった。子がいなかったため大和田家二男を迎え20世徳厚となった。時代は伊達村侯の時代になっておりようやく宇和島藩の発展が見えてきたころと思われる。21世徳翼は桑折桂円の名で知られる文人であるが、宗臣ほどは記録がない。若い頃から書に通じ詳細な系図を作ったとされるが残念ながら残っていない。この系図は仙台に伝わり仙台に残っていた桑折綱長の子孫に伝わった。桑折綱長は伊達政宗の死に際し殉死した桑折景長の7男とされる。綱長は殉死したため政宗の墓所瑞鳳寺に葬られており子孫も瑞鳳寺に葬られている。この子孫の桑折順治長教氏が文化文政のころに子孫のために残した歴史が残されている。これによると綱長は景長でなく宗長の子でその子孫となっている。年代的にはこの方が正しく子孫も残っていたということに成る。
このように見てくると江戸初期の宇和島藩は極めて流動的で多くの藩がとり潰しに会った中でよくぞ無事に立ち上がったという感がある。等覚寺を訪れ藩主の墓を見ると2代目宗利の墓の寂しげな感じが印象深い。宇和島は町全体が巨大な要塞で最後の守りの城としては有力だが城下町としての発展性には乏しく、豊かな後背地も持っていない。晩年の秀宗が卯之町に入り浸り西園寺党の黒須城が卯之町にあった理由がわかるように思う。このような地を所与のものとして南方に段々畑を開発し江戸後期の繁栄に至るまでには大変な努力があったと思われる。
桑折氏26世の伯父は重長という。祖父の直はこれらの経緯を知ったうえでこの名を付けたと思う。どのような思いで付けたのか気になるがわかっていない。