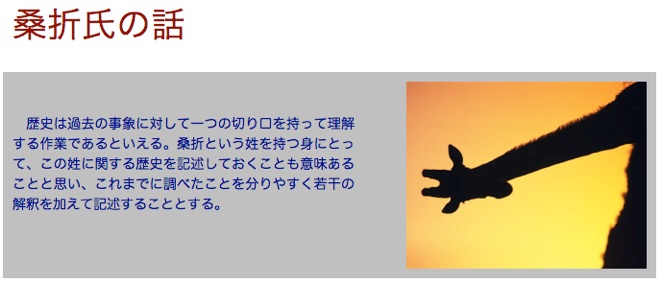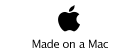桑折氏の話-4
<伊達氏天文(てんぶん)の乱>
伊達政宗の曽祖父に当たる、伊達氏13代伊達たね(禾偏に直)宗は伊達家の中央集権化を進めた傑物とされる。伊達家の法制度である塵芥集をまとめたことでも知られている。それまで守護制度で一般的だった「一族の集合体」を「強固な大名の組織」に向かわせた実力者と思われる。中央とのパイプも強く、足利幕府の弱体化、相次ぐ守護大名の没落、新興勢力の勃興などの情報も手に入れていたと思われる。たね宗は政略結婚により周辺大名家、家臣団との関係を強化していた。たね宗の母親は上杉家から迎えた父親尚宗の正妻で、越後の実力者だった上杉家との関係も強固であった。タネ宗の正妻は会津の蘆名氏である。天文7年から11年にかけ、上杉の世継ぎの男子が途絶えた時期、上杉家が上杉家の重臣と血のつながる伊達家3男実元を養子に要請することがあった。たね宗は3男実元を上杉に跡継ぎの養子として送り出すことを画策する。準備万端整い、上杉家から家老の直江氏が交渉に来ていたことが残されている。因みに竹に雀の紋はこの時上杉から伊達に贈られた贈り物である。16歳の実元を補佐し、実権を握る為、200人の精鋭をつけて上杉に送り込むというこの計画に対して「伊達家の衰退につながる」とする勢力が一族内にあり、長子の晴宗を立てて、たね宗の翻意を迫ることとなった。この結果、親子で争いが起き、藩は2つに分かれて内紛状況になった。7年に及ぶこの乱を伊達氏天文(てんぶん)の乱(洞(うつろ)の乱とも言う)という。この背景は専制君主化し、恐れられていたたね宗に対する息子晴宗を担いだクーデターだったといわれる。この実質的なクーデターの首謀者として、桑折景長と中野宗時が上げられている。この両名が晴宗を担いでたね宗の退位を迫ったということのようである。
上杉方でも反対者は多く、後の謙信の父親、長尾氏は反対派の筆頭であったとされる。伊達家内の反対根拠は「実元を養子に出すことに反対ではなく、越後の地を混乱させ、無用な敵を作ることに対する反対」という大義名分論であったようである。
後に曾孫に当たる政宗が残している。「たね宗公は独断専行、恐怖政治を強いており、皆ぴりぴりしていた。反対派が勝つ寸前まで行っており、仲裁が入らなかったら殺されていただろう」。
越後上杉は守護代長尾為景が簒奪し息子景虎は後に上杉謙信として上杉家を獲ることになった。伊達では中野宗時と桑折貞長が守護代となるが晴宗の子、輝宗の時代に中野は追放される。桑折景長は晴宗より10歳年長だが輝宗を支えて織田信長とのパイプを鷹を贈ることで築くような立場であったとされている。中野宗時は下克上のタイプだったかもしれないが、景長は伊達の一族としての立場を崩していないように思われる。
因みに養子に望まれた3男実元は上杉家の重臣中条氏の娘との間に出来た子であり、上杉家内の勢力争いの中にあったことは確かと思われる。実元は亘理伊達として分家する。この実元の長子が後世、伊達政宗の猛将として知られる伊達成実である。成実は関が原の戦の前に一時出奔する。実元が上杉を継いでいたとしたら政宗との関係はまるで異なったものとなっていたはずで、このあたりのことが背景にあるのかもしれない。出奔中に上杉家の家老直江氏より5万石での上杉仕官の話があったなどという記述は連想させるものがある。
幕末、東北の伊達は維新の流れに遅れ、明治初年には時流に乗り遅れた状況になる。亘理伊達は中でも大幅な削減を強要され、藩をあげて北海道への移住を決断し実行する。現在北海道にある伊達市はこの亘理伊達家の移住先とされる。
たね宗の5男(6男とも)四郎は桑折貞長の代で桑折家の養子となり夭逝する。
<伊達上杉連合>
現代の立場で冷静に考えると、この時代に伊達、上杉連合軍ができていたとすると当時の日本で最強だった可能性が高い。一方、上杉方の反対で越後が内戦状態になった可能性もあり得る。成功していたら長尾家の出身で、跡を継いだ謙信は存在しなかったことになる。時代は織田信長の活躍前であり、織田包囲網の一角を為した上杉との連合がどのような形を生んだか大変興味深い。