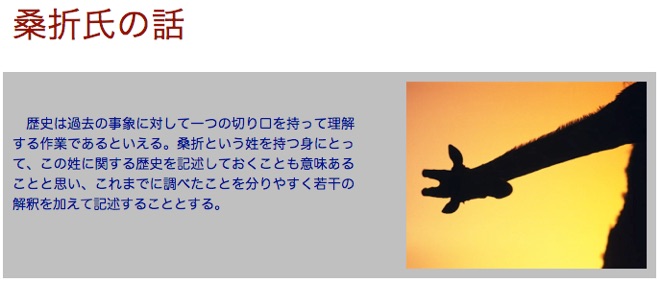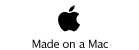桑折氏の話-9
<桑折左衛門と河後森城>
宇和島藩の藩祖秀宗は伊達政宗の庶長子である。一族の名門飯坂家の母親を持つ。10万石とはいえ遠方からの立ち上げは大変だったと想定される。政宗からの借金の記録などが残されている。桑折左衛門は後見役筆頭家老職であるが当初7000石の格であった。7000石だった理由は伊予と土佐の国境黒土郷河原淵領を所領として河後森城の城主となっていたためである。
河後森城は中世から伊予と土佐の国境の山城として幾多の争いを経験している城である。南予の地は古くから頻繁に当主を変えている。現在の宇和島城は藤堂高虎の築いた天守が震災で壊れたため伊達2代の宗利が再建したとされる。南予の地は天正12年(1584年)長宗我部軍が三間地方を落とし、西園寺氏の黒瀬城を落として統一した後、小早川隆景、戸田勝隆、藤堂高虎、富田信高、伊達秀宗と変わるがいずれも主城を宇和島城とし、河後森城は副城として城代を置いた。宇和島から南予を治めることを理解するにはこの土地を見てくるのが一番である。現在は道路が整備されたため宇和島から30分もすれば河後森城のある松野町まで行ける。30㎞弱のこの距離を移動して現地に行ってみると河後森城の持つ意味がよくわかる。
宇和島市内にいると水田など見当たらず、海と山が周囲を囲んでいる。これで10万石を維持できたのが不思議に思える。江戸の後半は海産物の流通があったろうが立ち上げの頃は大変だったと思われる。松野町に予土線で行ってみる。北宇和島の駅を出ると山の中に入り、務田駅までは山間をぬうだけである。鬼北の地に入り三間、松野町と来ると平地が出てきて畑や水田が出てくる。水源の中心となる広見川は四万十川の支流でこの地のすぐ下流が江川崎となる。分水嶺を国境とすればこの地は土佐となる。宇和島から見ればこの地を手に入れるか否かが生命線となる。中世、河後森城が幾多の戦いの場となった理由がよくわかる。城の規模は宇和島城より大きく、山城として実戦向けに作られている。
改めて奥州の遠方から伊達が宇和島藩を立ち上げた際どのようなことが行われたか考えると興味深い。
戦国の世では諜報活動は筆頭に掲げられる活動であり、伊達藩の情報は十分だったろう。このような地を治めるすべも戦国期、岩出山城、仙台城などを展開する中、実戦で鍛えていたと思われる。このような国替えにあたってどれほどの人数で展開したか意外と資料がないが、かなりの人数が必要だったのではなかろうか。米沢藩10万石に上杉のかなりの人数が行ったはずだ。桑折氏は伊達藩内では永代徴税権を持っていた譜代の大名格とされていたが初代の位牌からすべてを持ってきたとされているから配下の多くを連れてきたのではなかろうか。それであれば7000石の意味が分かる。
明治初年の宇和島藩の記録によると総人口16万9512人、農民15万1806人、町人4320人、士卒6682人、その他6704人とある。平均的な当時の比率は農民85%、武士7%、商工併せて7%、その他1%とされている。武士は江戸詰めが一定数いる為やや少なめ、その他の多いのは漁民だろうか。伊達村年の正徳年間(1710年代)にも記録があり人口99372人とされている。おそらく1615年当時の人口は10万人弱そのうち武士(一族郎党、家族を含む)は3000人~5000人ほどだったのではなかろうか。藩替えの際には3000人程度の武士団が来たと考えるべきだろう。長宗我部が最後に攻めた場所とすれば西園寺党を中心とする土着の農民の中には一揆の芽は常にあったとみるべきで、一定の武力を持って進出したと考えるのが自然と思われる。とりわけ支城の位置づけにあり宇和島からの部隊が派遣困難な河後森城下には最低でも1000人ほどの部隊が必要だったと思われる。
吉田藩が立ち上がった際、宇和島藩から武士244人を付けたという記録がある。この数は家族や郎党を含まないと思われるので家族まで含むと2000人以上となると思われる。平時の3万石で2000人とすれば立ち上げ時の7000石で1000人は妥当となる。松野町の知行地から三間を経て吉田町、卯之町に至る一帯は平地、宇和島藩内で最も豊かな地だったと思われる。長宗我部軍が河後森城から卯之町の黒須城を落としたことからもこの地の守りは重要だったはずだ。桑折左衛門が亡くなったのち桑折氏は7000石から1000石に減俸となる。この件に関しては次回で述べるが、この地理的関係と宇和島藩、吉田藩の関わりもあると思われる。
西園寺党の本拠地卯之町を中心とする海岸地方の抑えは山家清兵衛が担当したのだろう。こちらは宇和島からの対応だったのだろうが一定の士卒は置いていたと思われる。
京都で育ち腹心の部下を多く持たない秀宗のために政宗は政宗57騎と呼ばれる武士団をつけたとされる。桜田玄蕃や志賀右衛門は入っているが桑折左衛門と山家清兵衛は入っていない。一方で政宗から直接この二人は任命されている。桑折左衛門(当時は石母田景頼)は政宗が小田原城攻めに参陣する際に万一の時の後事を託し、二本松城に残した3城代の一人だったとされる。秀宗の母や山家清兵衛の妻と左衛門は従兄妹の関係にある。詳細は不明だが一つの藩を立ち上げるには幾つものタイプのプロが必要なはずで桑折左衛門や山家清兵衛、志賀右衛門などは治世のプロだったのではないかと思われる。山家清兵衛は秀宗の半年前に赴任し奉行として活動している。一方左衛門は秀宗の半年後に赴任し河原淵領に赴き奉行として河後森城の城主となり、この地に住んだとされる。
河後森城の本郭は城の最高部で広見川を望む光景は仙台城を思わせる。広見川は四万十川の支流だがかなりの広さがあり清流が流れている。桑折左衛門にとっては懐かしい光景に思えたのではなかろうか。
桑折も山家も宇和島に移ったが仙台にも分家は残していた。政宗の死に際して殉死して葬られている桑折氏は桑折景長の7男と伝えられている。山家も宇和島では一族皆殺しにあったが仙台の子孫が現存している。戦国期の知恵なのだろう。仙台の桑折氏はその後、伊達騒動の際に断絶しこちらは宇和島だけが残った。
左衛門は河後森城に慶長19年(1615年)に移ったが元和元年(1616年)江戸幕府は一国一城制度を敷く。これにより、宇和島伊達藩は宇和島城を残し河後森城は取り壊すこととなる。左衛門は城の最後の城主として城の取り壊しを行った。左衛門は寛永2年(1625年)に亡くなったが、この地に住み続けたとされ、墓所も城の裏手の照源寺にある。幕末の長よしの時に等覚寺に墓を移し事績を記した碑を建てた。現在も照源寺の墓所に残っており、数十年前まで宇和島桑折家では年に一度ここにお参りに来ていたとされる。
現在等覚寺にある桑折家の墓所は「桑折宗臣の墓」とある。松野町の照源寺が当初の桑折家の墓所とすると等覚寺に最初に桑折氏の墓を持ったのは宗臣だったのだろうと思う。宇和島に住むようになり代々の桑折氏はここに墓を作った。幕末の長よしが左衛門の事績の碑を作り左衛門の墓を等覚寺に移したとされるがどれが左衛門の墓かははっきりしない。長よしの墓と思われる墓と石や傷み具合が近いことと大きさがそれなりであることから最も奥にある墓がそれではないかと思われる。長よしも徳翼の長女と結婚した養子で、徳厚の娘が嫁いだ小池家からきている。