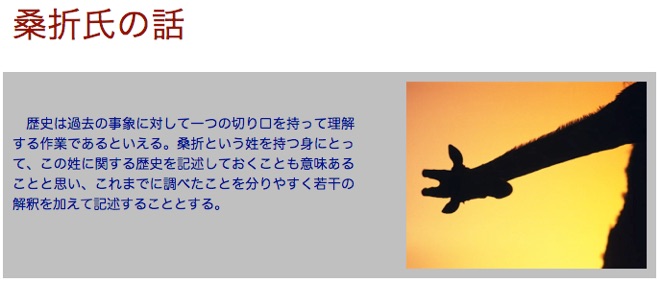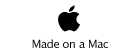桑折氏の話-8
<伊達騒動と天文の乱>
伊達騒動は原田甲斐を悪人や義人とする説を残している。一つの側面としてみると仙台伊達藩内の勢力争いとも言える。仙台伊達藩は政宗を初代とする形をとっている。350年に渉るそれ以前の歴史は一旦切り離される。伊達騒動の結果として桑折景長に関わる飯坂家、石母田家、原田家、桑折家などは仙台伊達藩では断絶する。
これ以前、一族の譜代であった飯坂家の家督は宇和島の飯坂の局が継いでいたがこれらは全て没収され、断絶となった。
伊達騒動は伊達の旧来の家臣団との関係を清算することとなったとされている。どうやら「旧来の家臣団」の中核の一部をなしていたのが桑折氏の一族なのではないかと思われる。福島に住んだ史家の小林氏はこれらの関係から「桑折氏が伊達騒動で消された」との説を唱えたものと思われる。
天文の乱はたね宗側から見れば周辺大名家との連合による拡大を狙ったものといえる。晴宗側から見れば伊達一族の結束を強化し一丸となって戦国の動乱を乗り切るという戦略といえる。桑折西山城を居城としたたね宗の構想は開かれていて大きなものと見える。晴宗が居城とした米沢は山に囲まれた冬は雪深い盆地である。どこか閉じこもった印象がある。
政宗が伊達一族350年の歴史を捨て、政宗に始まる歴史を描いたということは自らの動乱の最中での大活躍の結果といえる。組織として見ると、それだけでなく一族を切り離し、新たな時代に新たな体制をもって臨むという選択を行ったといえるようにも思われる。この選択はタネ宗の選択に近い。
政宗の祖父の時代に起こった天文の乱の記憶はまだ残っていたと思われるから、宇和島伊達藩創設とその後の一連の騒動と結果は一族を宇和島に送り、新たな体制を仙台に築き後顧の憂いをなくすという意味があったと見ることも出来るように思われる。仙台の伊達は政宗を初代とする新たな系図を作っている。
250年後、維新の動乱に際して、宇和島伊達藩が250年前と同じようにチャンスをとらえた飛躍を行ったことを見るとある種の感慨を持つ。
秀宗の後2代で仙台伊達綱宗の流れとなり、秀宗の4男宗臣が桑折家を継ぐことと成る。
宗臣は「むねしげ」と読み、10世宗茂と同じ名、同時に豊臣の一字を持つ変わった名前とも見える。詳細な一族の記述を行ったとあるが戦災で消失した。
<景長の名前>
伊達正統世次考では桑折景長が天文の乱の黒幕とされているが、桑折家の家系によれば天文の乱は貞長の名の時代に起きていたと考えられる。晴宗時代、守護代となった貞長の記録が残っていることから事実だろう。景長の時代は輝宗時代と思われ、伊達と一心同体になっていた時期と考えられる。子孫に景の字を残しているところからも活躍の時期と思われる。家系では鷹を信長に贈った件で「世に知られた」と書かれているから輝宗時代の逸話だろう。息子の宗長(点了斉)は輝宗、政宗に仕えているから、輝宗時代の終わり頃には宗茂と更に名を変えたと思われる。
仙台伊達藩の正史でなぜ貞長でなく景長が天文の乱の黒幕とされているのだろう。政宗の正妻は田村家から迎えており、天文の乱に際して、調停を行った側の縁戚関係にある。新時代は伊達の一族というよりタネ宗時代に相当する奥州王としての世界を造りに行ったと考えると理解できる様に思われる。伊達騒動を契機とし「結果として桑折景長に関わる仙台伊達藩の一族が一掃された」という見方も出来る。「その為に貞長でなく景長が天文の乱の黒幕であったとした」と考えるのは考えすぎか。
一方、この間に政宗の死と葬儀が行われている。葬儀に当って上席に長男秀宗がついていたとされ、様々な流れが起きていたとも思われる。このあたりのことは定かでない。