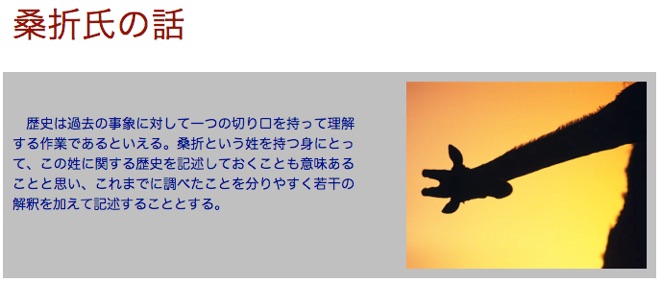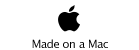桑折氏の話-3
<桑折氏の始まり>
伊達3代義広の庶長子、桑折氏初代の桑折親長は桑折氏を名乗った。親長は伊達郡桑折郷1948石4斗4升7合その他数邑を領有したとされる。対外的には伊達氏を名乗っていたとされ、家系によると伊達中村太郎左衛門蔵人親長となっている。「伊達左衛門親長で登場する伊達蔵人は当時の伊達惣領4代政依の代理として出た桑折親長とする説(戦国大名伊達氏の研究)」は家系によれば正しい。この時代は対外的には伊達で通していたとされる。親長は引退後、心円入道と号した。伊達本家を継いだ政依は鎌倉に住まいして幕府の任務に従事し、本拠地は桑折氏が守っていた時期も有った様である。後世江戸期の幕府と国家老の関係と似た体制がこの頃からとられていたといえる。
2世政長、3世宗康、4世康長と続き、宗康の頃は南北動乱で東北は北畠顕家を担いで南朝側に立つこととなり、動乱の時代となる。宗康は佐々川で戦死、康長も高師直軍と戦ったとある。
5代目頼長から桑折氏を対外的にも正式に名乗るようになったとされている。6代邦長、7代宗秀、8代宗保、9代宗季と続く。
この時代の桑折氏の事績の一端は「戦国大名伊達氏の研究」に部分的に紹介されている。
<350年間の蓄積>
伊達郷を領した朝宗(或いは宗村)は当初、要衝の地である桑折町近辺に居城を持った可能性を指摘されている。タネ宗までは梁川城が居城とされていることが多い。後の政宗の曽祖父(タネ)宗は桑折西山城(赤館)を居城とし、米沢を中心とするのは政宗の祖父、晴宗の代からである。早い時期から桑折郷は交通の要衝として重視され、西山城は中核拠点とされていた。奥の細道でも「伊達の大木戸を経て桑折の門にいたる」と表現されているように、江戸時代、桑折藩は江戸幕府の直轄領とされ、関所が置かれていた。語源は様々であり、「くは」という崖のような地形に由来するというものから郡に由来するなど様々な説がある。郡に由来するとする説が有力である。桑と折と云う漢字からは植生に関する由来もあったものとも推定されるが定かでない。
加えて桑折町の近辺には江戸時代に開発され、今に残る半田銀山があり豊かな富を持っていたと考えられる。
伊達領内での富の比重で桑折領は図抜けていたとされ、一族内での桑折氏の立場は大きいものであったとされる。
鎌倉幕府の勢いが衰え、南北朝の時代には奥州もそれぞれの派に分かれて戦が行われた。
この戦は一方で勢力拡大の争いでもあった。伊達は名門ではあったが、より古くからの奥州探題は大崎氏で、勢力拡大と共に奥州の実際の盟主の座を狙っていたと思われる。
この時代、伊達家は鎌倉府に対する敵対行動を起こし、領土拡大に努めている。
足利尊氏の勢力が高まってきた折、伊達氏の本流は南朝側に立ったが、桑折氏は北朝に立っていたとされる。一族としての両にらみとも思える動きだが明確ではない。体制の帰属以上に一族の結束の方がはるかに強かったと思われる。村上水軍や真田一族が天下分け目の戦に当たって双方についていたのと似た動きと思われる。
鎌倉にいた伊達惣領家に対し、本国にいた桑折氏は足利尊氏が実権を握る前に情勢を把握して鎌倉と距離を置くようになっていたとされ、危険分散を図っていたとも考えられる。
鎌倉時代は鎌倉が中心であったが、伊達氏は鎌倉だけで無く、京都とのつながりも強く、中央の情勢は現在考えられている以上によく把握していたと思われる。